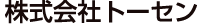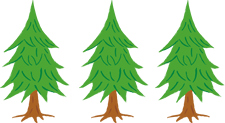いよいよ、今回の実証実験にご賛同頂いた山林所有者の方の山から、弊社の那珂川工場に原木が到着しました。
今回の最大のポイントは、間伐の遅れた山林から発生する低質(曲がり、反り、腐れなど)の木材をいかに搬出でるか? 伐採のコストをいかに下げることができるのか? の2点です。
これらの作業を確認するため、この日は担当の森林組合さまと現場の確認を行いました。
具体的な伐採作業のポイントは、<従来>と<今回>では次のような違いがあります。
<従来>
間伐作業で伐採した木材は、一本の木から通直(真直ぐ)で腐れなどの傷みがない部分を選び、その部分を切り取る作業(造材という)を行います。この作業の過程の中で、残された木材は極論を言えば山に放置されます。
<今回>
伐採した木材の良い部分のみを選び抜く、従来型の造材作業に比べ、明らかに良質な木材である場合を除き、概ね3mにカットする作業としまた。今回の山林は全体的に間伐が遅れていることは明白であるため、良材を選別する作業にこだわらず、造材作業をシンプルにし効率的な作業に心がけて頂ました。これにより、低質材であるか良質材であるかの見極めには極力時間を割くことなく伐採・造材に集中するため作業性が向上すると同時に、従来の作業では、山に放置していた(捨てていた)木材までも搬出するため、伐採コストは下がるものと考えられます。
以上、伐採作業の違いを明確にした上で下記の写真のような木材が搬出されて参りました。
搬出された木材

選木機により選別された木材

低質材として選別された木材

低質材の例(曲がり材、芯腐れ材)


栃木は、この度の寒波で積雪もあり伐採・搬出作業は滞りが発生し、途中経過報告ですが、1haの山林から概ね100m3の木材が那珂川工場に運びこまれ、このうち約20%がいわゆる低質材としてカウントされている状況です。従来であれば、これらの材は搬出されず生かされないで山に放置されてしまいます。これらを搬出して生かすことで、現在の補助制度の最高ランクの補助金が適用される訳です。
森林組合の担当者の方にお伺いすると、現場では、このような伐採(低質材を思い切って出す)を行うに当たって、現場はやり若干の戸惑いが見られたとの事でした。「本当に、こんな材を製材工場に運んでよいのか」そんな声も当然出た事でしょう。ある意味では、今までとは180度違う山林の活用にプロでさえも頭の切り替えが必要であることを物語っていると感じました。
このような現場の説明会・勉強会などを通じて、山林所有者の方の理解、現場の理解、受入側の理解をさらに深めていく必要性を感じました。今回の実証データを取りまとめて、皆さんにご紹介できる機会を設けますのでお楽しみに・・・・・・。
この日の、那珂川工場の最低気温は-8℃を記録し、厳しい寒さの中での確認作業でした。ご協力頂いた森林組合さまありがとうございました。